5年間の奉公時代に体得した「大きな糧」
赤木 明登(以下、赤木) 先ほどの飛騨職人学舎の若い人たちの挨拶がとっても素晴らしくて。 最初に僕も自己紹介をさせていただきますね。実は僕は、いまからちょうど30年前の1988年、東京でサラリーマンを4年間やっていたんですね。それから輪島で職人さんになろうと思い、一念発起しまして、いわゆる”脱サラ”をして、輪島に引っ越しました。

赤木 明登(あかぎ あきと) 塗師。1962年岡山県生まれ。中央大学文学部哲学科を卒業後、編集者を経て1988年に輪島へ。輪島塗の下地職人・岡本進さんのもとで修行後、1994年に独立。現代の暮らしに息づく生活漆器「ぬりもの」の世界を切り拓く。1997年にドイツ国立美術館「日本の現代塗り物十二人」展、2000年に東京国立近代美術館「うつわをみる暮らしに息づく工芸」展、2010年に岡山県立美術館「岡山 美の回廊」展、2012年にオーストリア国立応用美術館『もの─質実と簡素』展に出品。著書に『二十一世紀民藝』(美術出版社)、『美しいもの』『美しいこと』 『名前のない道』(ともに新潮社)、『漆 塗物物語』(文藝春秋)、共著に『毎日つかう漆のうつわ』、 (新潮社)『形の素』(美術出版社)、『うつわを巡る旅』(講談社)など。

左から:赤木明登氏・中川政七氏
いまでも輪島は「徒弟制度」*1というのがきちんと確立されたまま持続して残っています。それが輪島という産地の素晴らしいところだと思います。なので僕はまず、弟子として職人さんの中に入り込んでいきました。
*1)徒弟制度:中世ヨーロッパの手工業ギルドにおいて、親方・職人・徒弟の3階層によって技能教育を行った制度。また、一般に日本の年季奉公・丁稚(でっち)などの制度をいう
輪島に行って最初の5年間は、親方について「奉公」というのをやっていました。当時、東京はちょうどバブル直前のイケイケの時代だったんですね。そんな空気感の中、僕は東京時代を割と楽しんで過ごしていたんです。東京で自分が体験した「センスがいい」とか「自分は好みがしっかりしている」とかいうことを、弟子入りをして完全に打ち壊されてしまいました。
親方のところでは自分を全く消し去って、常に「親方がなにを考えているか」、そのことだけをずっと考えて奉公します。そうして仕事をしていくうちに、いつしか親方が思いつく前に自分の身体が動くようになる。そのくらい自分を消すことができるようになりました。そういう体験をたった5年間したことが、独立してから25年間、僕自身の仕事の大きな糧になっていると思うんです。
そもそも徒弟制度というのは、職人の世界では昔はどこにでもあった光景だと思います。そうした風習が職人の世界から殆ど消えていった中で、飛騨産業さんが「学校」という形で、なにか新しい職人・徒弟制度の在り方を模索されているんではないかなという気がして、すごく興味深く、面白く思いました。

写真提供:飛騨産業株式会社
今日はこのお話を、先ほどの生徒さんたちも聞いていらっしゃると思います。奉公や修行の期間は厳しい生活空間に身を置いて、結構辛かったり苦しかったりすることもあると思います。でも、 いま経験していることが将来、物づくりを行っていく上で必ず役に立つし、意味のあることだと思うので、一人前の職人さんになるまで、皆さんぜひ頑張ってください。
30年間ごとの「工芸界」の転換について
工芸家の僕がお話できることというのは、工芸の分野に関わることだけだと思うんですね。この30年間輪島にいて僕が経験したことを、さらっとお話したいなと思います。
僕が輪島に行ったのは、先ほどもお話したように1988年ですけれど、工芸の世界は1990年くらいを境に大きな転換をしていったと思います。そこでまずは、1990年頃までの30年についてお話をしたいと思います。
作家の表現性の時代( 1960年~1980年代)
当時がどういう時代だったかというと、戦後、アメリカから現代美術*2というのが日本に一気に入ってきました。それまで「工芸」というのは、機能とか用途を満たすために作られているものでしたが、その時代、日本でも現代美術の影響を受けた工芸作家というのが現れてきました。
*2)現代美術:一般には第2次世界大戦後の美術。さらに狭く戦後の新しい動向をいうこともある。戦後美術一般ということでは、アメリカの現代美術が注目を浴び、戦前のヨーロッパ中心の美術地図が塗替えられたことが特筆される
要するに工芸作品を自己表現や思想、考え方を表現していく「手段」として使っていくという時代が30年くらい続いていたと思います。で、僕はこの時代を「作家の表現性の時代」と呼んでいます。当時、同時代を並行しながら、僕自身は消費者として熱い想いでその流れを見てきたし、すごく楽しい時代でもありました。ちなみにその前の30年(1930~50年代)は、民藝*3の時代だったのではないかと僕は思っています。
*3)民藝:1926(大正15)年に柳宗悦・河井寛次郎・浜田庄司らによって提唱された生活文化運動から生まれた言葉。柳らは、名も無き職人の手から生み出された日常の生活道具を「民藝(民衆的工芸)」と名付けた
その潮目が、1990年くらいを境にガラッと変わりました。ちょうど、バブルの崩壊が1991年~93 年くらいだったと思うので、バブルの崩壊と重なる時期です。工芸の世界でも60年代から続いていた自己表現みたいなものがやり尽くされて、次に出てきたのが普段の生活に使える、実用的でシンプルな器たち。そういうものが一気に出てきた。その最初の世代が、僕なんかではなかったかと思うんですね。
生活工芸の時代(1990年~2010年代)
僕が独立をして最初に展覧会をしたのが、1994年なんです。そのくらいから、普段の生活に使える実用的な工芸が全盛を極めて、いまにつながっているという状況だと思うんです。2000年代に入って2010年くらいから、香川県高松市で「瀬戸内生活工芸祭」という祭典が行われ、石川県の金沢では「生活工芸展」というものが、自治体のイベントとして大々的に行われていくことになりました。その30年ほどの動きというのが「生活工芸の時代」と名付けられるようになっているのだと思います。
いまから振り返って「生活工芸」というのは、どういう特徴を持っていたかを考えてみると、こんな風にまとめられると思います。
◆「生活工芸」に見られる特徴
1. 表現のため、飾るためではなく、使うために作られたもの
2. 作り手が産地と距離を置く中での物づくり
3. 地域性のなさ、土地固有の特徴の希薄さ
4. 作家による天然素材を用いた手づくりの器が裾野を広げていった時代
一つは、表現のため・飾るために作るのではなくて、使うために作るということ。同時に、作り手が産地と距離を置いていた時代じゃないかなと思うんですよね。
僕はいま輪島で活動をしていますけど、備前や常滑の作家とかいうんじゃなくて、ナントカ焼、ナントカ塗りでもなく、いろんな地方に散らばっている作家たちが、ある程度産地と距離を置きながら物づくりをしていた。それともう一つは、地域性のなさみたいなものが特徴だったと思うんですよね。
要するに、北海道で作っても九州で作っていても、「シンプルで白いうつわ」のような共通点はある。一方で、その土地固有の特徴みたいなものはどこか希薄だった。でも逆にいえば、産地からの距離を置いていることと、地域色やローカルな感じがないということが、その時代の受け手(消費者)には、非常に格好いいものとして馴染んでいった。そのため急速に、天然素材を用いて手づくりされた作家ものの器というのが裾野を広げていった時代だと思います。
工芸の裾野を広げるという意味では、生活工芸はたいへん貢献していたと思います。自分で言うのもなんですが、生活工芸作家のトップランナー集団の中に、当時は僕自身もいたと思います。けれどそれから30年ほど経とうとしたときに、だんだんとその状況に対して、違和感を感じるようになりました。で、僕自身はいまはそこから、完全に離れてしまったという状態になってしまっているんですね。
問われるのは、「産地との距離感」「地域性のこだわり」を大切にした物づくり
僕自身がどこに違和感があったのかというと、やっぱり産地との距離感と、それから地域性へのこだわりだと思うんですね。先ほど鞍田さんが民藝のお話をされましたけど、いま若い人のあいだでも、「民藝」というのがすごく注目されている。
先日、朝日新聞の大きな記事で「東京都内に民藝を置く店がすごく増えている」とありました。若い人たちの間でいま、民藝が求められているのは、物づくりの一番重要な部分と重なると思うんですね。それは、土地で取れた材料を旬のまま使い、物を作るということですね。それによって「民藝」はなにをやっているかというと、大地とか土地とのつながりみたいなものを、もう一度取り戻そうとしているのではないかと僕は思います。

カンファレンス当日。ロビーでは日本工芸産地協会会員企業の製品ディスプレイを行った|写真提供:飛騨産業株式会社
それは多分、いま生きている人たちが、自分が何者かということがわからない根無し草のような 状態になってもいて、そのままでは生きられないからこそ「自分の帰属する場所、土地のようなものともう一度つながりを持ちたい」と思っているのではないかと。
僕自身がそうでもあるので、そういう部分で生活工芸から「新しい民藝」へ転換を図っている。 いまはちょうど、その境目あたりにいるのではないかなぁということを僕からはお話をして、おしまいにしようと思います。
◆「工芸」をとりまく時代の変遷
1930~1950年代「民藝の時代」
1960~1980年代「作家の表現性の時代」
1990~2010年代「生活工芸の時代」
2010年代後半 ~「新しい民藝の時代」?
鞍田 崇 ありがとうございます。ご自身の体験も踏まえつつ、時代の動き、工芸として目指されるところについてお話しいただいたかと思います。
90年代以降、工芸に新しい動きが現れたわけですよね。それまで表現性や芸術性を志向していたのが、使えるもの、生活に寄り添うものを目指すようになって。ちょうど社会ステージが「ポスト工業化」となったタイミングと重なることを考えると、世の中全体では、物づくりから撤退しながらも、といいますかそういう時代になったからこそ、いちばん身近な生活道具を作るいとなみの再評価が進んだのかもしれません。それが、いま赤木さんがご紹介くださった「生活工芸」と呼ばれるシーンですよね。そこには、こういう時代ならではの新鮮さもあった。なんといっても、工芸が本来の生活との接点を回復したことはいちばんの功績かと思います。
ただ、一方で、産地との距離、地域性の希薄さという問題を孕んだ動向でもあって、その点が見直されつつあるのが、2010年代後半のいまなんだろうと思います。では、次に中川さんお願いします。
中川政七 いや、とても難しいですね 。 あのー、僕も最初に自己紹介から始めたいと思います。

左から:中川政七氏・鞍田崇氏
→[パネルディスカッション① 「工芸と工業の次」中川政七商店会長・中川政七 3/6 ] 後日、公開予定です。
前回公開:パネルディスカッション① 「工芸と工業の次」哲学者・鞍田崇 1/6
メインビジュアル:ぬりもの
写真提供:さんち編集部
テキスト編集:中條美咲
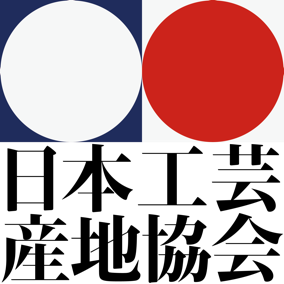
 メニュー
メニュー