なにに対する「共感」か
鞍田崇(以下、鞍田) ありがとうございます。中川さんのお話では、いまは憧れじゃなくて共感が求められているんじゃないかというご指摘がありました。赤木さんの実感はいかがでしょうか。
赤木明登(以下、赤木) まぁほんとに、中川さんとは25年くらいのお付き合いというか、最初は酒飲んで暴れているおっちゃんだったという話だったんですけど(笑)。チョット僕の方から、中川会長にお聞きしたいんですけど、「共感」と言った場合、なにに対する「共感」だと言えるんでしょうか?
中川政七(以下、中川) なにに対する・・
前回までのお話はこちら
パネルディスカッション① 「工芸と工業の次」哲学者・鞍田崇 1/6
パネルディスカッション ①「工芸と工業の次」 塗師・赤木明登 2/6
パネルディスカッション ①「工芸と工業の次」中川政七商店 代表取締役会長・中川政七 3/6

写真左から:赤木明登さん・中川政七さん・鞍田崇さん
鞍田 中川さんがおっしゃったのは、物だけじゃなくという視点でしたよね。
中川 物だけじゃなくて、例えば、その作り手の顔が見える。そこで会話が生まれる。どういう意図でこの物が作られたのか、作られた背景についての話を聞く。そこに対してなんらかのカタチで素敵と思える気持ちが「共感」だと思うんですけど。
赤木 さっきもお話があったように、輪島も売上が1990年代のピーク時から5分の1に減っています。漆器業界全体だと10分の1くらいまで落ちているということで、これはもう急速に滅んでいってるというのが産地の現実ですよね。でも一方で、中川さんのお店は、この16年で50店舗以上に増えている。生活工芸の作家さんでも、売れている人はたくさんいるということもあるんですよね。
僕は中川さんのお仕事を遠目から見させてもらっていると、「工芸的なものにこんなに伸び代があったのか!」とすごく思ったんですね。そこの伸び代を支えてきた部分として、いちばんのポイントはなんだったのかを聞いてみたいですね。

写真提供:中川政七商店
中川 僕の場合は、物を自分で作れません。作らない立場の人間として「工芸」に関わっています。うちの家業は麻ですけど、コンサルティングとかになると、麻以外の物にも触れるわけですよね。そのときに大切にしているのは、僕はどこまでも素人というか、ど素人であるということ。それはつまり、お客さんとかなり近い状態だと思うんですね。
一方で、ずっとその物に向き合っている人たちは、その物が当たり前になって「もう説明しなくてもわかるだろう」と思ってしまうことがたくさんあると思います。あるいは、その物を見続けてるがゆえに、職人さん、あるいはメーカーさんの興味は、お客さんの興味とはかけ離れてしまっているということも起こると思うんですよね。そこで僕みたいな素人、お客さんに近い立場の人間が、それでも物づくりの構造、仕組みだけは一応わかっているので、間に入って翻訳的役割を果たすというか。
だから他所へ行くと、客観的にそこの良さというか心揺さぶられる部分はあるんですね。でも、その良さが物を通じて伝わってない。なのでその良さが物を通じて伝わるように、コミュニケーションのボタンのかけ違いみたいなことを直すのが、僕の仕事だと思ってやってきています。
赤木 例えばですね、具体的にいうと波佐見で中川さんが最初に手がけられた仕事が、すごく成功したわけじゃないですか。
中川 はい。
赤木 それは具体的に、どこのボタンのかけ違いをどう直したらつながったんですか?
中川 波佐見はチョット喋りにくいので、他の地域でもいいですか?例えば、赤木さんの専門分野の「漆」なんですけど、越前漆器のお手伝いをしたときのお話をさせてください。漆って数ある工芸でも、僕の中ではいちばん避けて通りたかった最難関のアイテムだと思っていました。その時に考えたのは、「漆ってそもそもなんのために塗り始めたんだろう?」というところから考え始めました。この「そもそも」というのは、割とどこにでも常につきまとう考え方だと思っています。
たぶん大昔、石器時代とかに手で水を汲んで飲んでいて、それよりもくり抜いた木を使ったら「おー!ガブガブ飲めるでー」って誰かが気がついて、道具を使い始めた。でも、一生懸命くり抜いた木の椀を使っていても、しばらくするとパカパカ割れる。せっかく頑張って作ったのに、また割れると繰り返すうちに、わかんないですけど誰かが、「漆の樹液を塗ったら割れなくなった!」みたいなことがスタートなんだと思って。だから漆はそもそも補強材なんだろうなと。
「そもそもなぜ、使われ始めたの?」素材の起源を想像すること
中川 漆はそもそも補強材だった、ということをお客さんに伝えるために、最小限の塗り方をして商品として出すことを考えました。それをメーカーさんに伝えたところ、生地に拭き漆をしただけのとてもシンプルなお椀が出てきたんです。割れない程度に最低限に仕上げることで、値段もお手頃になった。そのコミュニケーションが多少なりともお客さんに伝わって、結果的にそのアイテムは売れたという。

福井県鯖江市にある漆器メーカー、株式会社 漆琳堂の「お椀やうちだ」を手がける
写真提供:中川政七商店
赤木 要するに、物を作ることの「目的」を使い手にきちっと伝えていくということですか?
中川 そうですね。なぜその物、そのカタチなのか。いまの時代はみんな、家に足りない物はほぼないわけで、なにがしかの意味がないと物を買おうとは思わない。「へー」とか「ほー」とか「新しい発見」とか「面白い!」とか。そういう心揺れる”なにか”が含まれていないと、もう人は物を買わないんだと思うんですね。
で、そこに対するアプローチとしてよくやるのが、「そもそも論」だったりします。結局、僕が経営の上でいつも心がけているのは、「工芸は置いているだけでは売れない。その製造背景やストーリーまで伝えないと。だからこそお客さんに近づかなきゃと思って、お店を作ったんだと思うし。
赤木 特に漆の場合、売るのがいちばん難しいですからね。
中川 ほんとうにそうですね。いちばんやりたくなかったです。
赤木 ハハ(笑)。 あのー、そもそも「漆がなぜ塗り始められたのか」ということに関して、民藝の「用の美」の考え方では、木の器を丈夫にするために塗っているんだというのが、一般的な「用」の考え方ですよね。それはある意味正しいけれど、ある意味違っていると実は僕は思っています。

赤木 それは『二十一世紀民藝』という僕の新しい本の中にも書いてありますけれど、そもそも僕は用途のために土器が作られたり、用途のために漆を塗り始められたのではなくて、それ以外にもっと根元的な願望というか、目的・理由があったのではないかと。
僕は、漆が最初に使われ始めたのは、赤色を器物に定着させるためのメディア・媒質、つまりは接着剤としてではないか思うんです。赤色には「生命」であるとか、「死からの再生」の象徴があるわけで、これは人間にとってはいちばん切実な問題です。そこに、ある意味呪術的な色である「赤」を定着させるときに漆を使い始めた。という方が、僕はより根元的な気がしているんですよね。

写真提供:ぬりもの
なので、さきほど中川さんが仰った「丈夫にする」という機能は、たぶん後からついてきたんじゃないかと思っています。赤色を定着させるための媒質として漆を使い始めたら土器は割れにくく、木の器は長く持つことがわかった。機能面と精神面と両方の世界が常にあったと思うんですよね。で、時代によって、どっちかが表になったり裏になったりしてきたと思うんですけど、柳宗悦*2自身はたぶん、機能よりもある意味神話的とか呪術的な部分をよく見ていますよね。
*2)柳宗悦(やなぎ むねよし):日本を代表する思想家(1889年3月21日 – 1961年5月3日)。「そうえつ」の呼び名でも親しまれる。1910年、文芸雑誌『白樺』の創刊に参加。1925年、民衆的工芸品の美を称揚するために「民藝」の新語を作り、民藝運動を本格的に始動。1936年、目黒区駒場に「日本民藝館」を開設し、初代館長に就任。
例えば、「生活工芸」の時代と言われた時代はどちらかというと、「機能」としての用の時代だったと思うんです。さっきお話ししたように、そこからもう一回転換があって、いまは「機能」の奥にある「根元的・精神的なもの」を探り始めたようなフェーズにいるのではないかという風に思っています。
鞍田 先ほど赤木さんはそれを、「地域との結びつき」というようにお話されたと思うんですけど、それは単に地域に結びつくという話ではなくて、ある種の心の問題というか。いま、中川さんのおっしゃった「共感」にも通じる部分。土地との結びつきと精神性、その両方が絡み合っているっているということかもしれませんよね。
僕は、いま求められている感性って、「インティマシー」── 日本語で「いとおしい」という感覚ではないかと考えています。その内実を考える手がかりのひとつとして、「民藝」というか、近年の民藝に寄せられる「共感」に注目してきました。実際、柳自身が工芸特有の魅力を語る際に、「インティマシー」とか、「親しみの美」って言っています。それは、中川さんのおっしゃるところの「共感」に通じる部分だと思うんですけれども、そこには、現代ならではの心の反応の仕方があるんじゃないかなぁと。
「作る」のではなくて「生まれる」ことへの共感
鞍田 関連で、大西麻貴*3さんという女性の建築家について少しご紹介させてください。
*3)大西麻貴(おおにし まき):「大西麻貴+百田有希/o+h」を主催。2017年より横浜国立大学大学院客員准教授。主な作品に「Good Job! Center KASHIBA」等
彼女は「美しい建築はもういい」っていうんですね。むしろ「愛される建築であってほしい」と。で、愛される建築ってどういう建築かと聞いた時に、彼女は「生き物みたいな建築」と言いました。共感とか自然とか、ちょうどいま論じあっている方向性とも重なる例じゃないでしょうか。
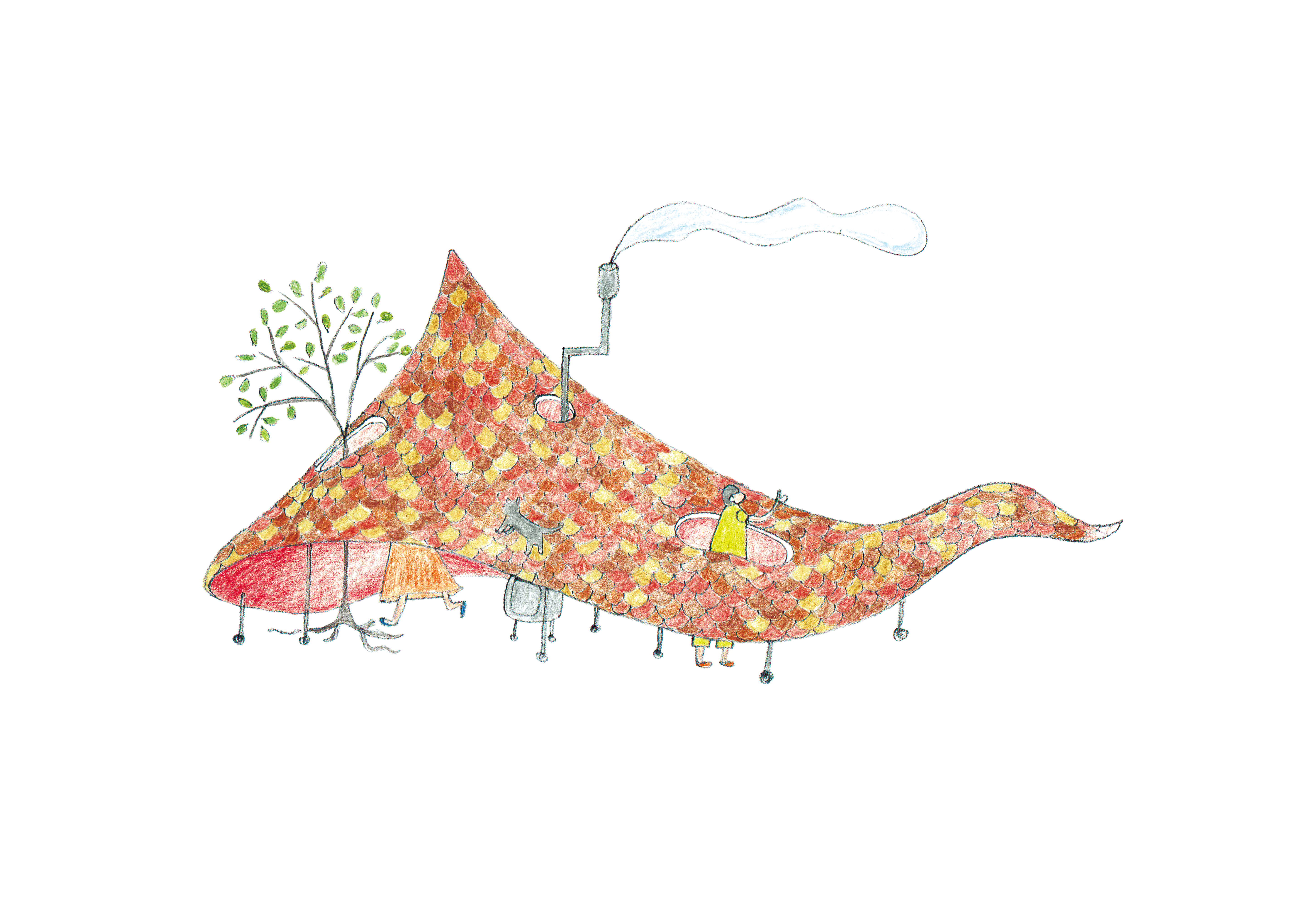
写真提供:大西麻貴+百田有希/o+h
鞍田 大西さんの取り組みからは、単に似たような言葉を使っているということに尽きないものを感じるんです。ただ、問題は、「共感」の中身。いま僕らが求めているものって、自分自身の身体性との結びつきという部分も大事な要素としてあるのかなぁと思うんですね。身体感覚をともなった実感や体感のような。インティマシーって言葉をあえてボクが使うのもそのためです。
ただ、それらは閉ざされた個人としての小さな体験に留まるものではなくって、もう少し大きなもの、土地や自然と結びついていくものじゃないかと思います。個を超えたストーリーへの接続がもたらす充足感みたいなもの。お二人のお話からは、そういった志向性も感じました。
中川 いま、赤木さんのお話を聞いていて、思想的なことがたぶん「土地性」ということにも間違いなくつながってくるし、「継続性」ということにもつながってくるなぁと思うんですね。且つ、それを言葉にしようとするとけっこう難しい。僕が柳の本を挫折するように。
それらは用だけでもなく、思想だけでもなく、混ざり合っているものだと思うんですけど、そうなってくると、なおさら言葉にするのって難しいんだろうなぁと思いました。でも、言葉にはできないけど「なんかいい」っていう、それがまさに鞍田先生のいう「インティマシー」っていう感覚かもしれないですね。そういうことがいま、すごく大切なんだと思うんです。でもこれは、説明しづらい。文字にしづらいから伝播しにくいんですけど…。

「言葉にするのは難しい」。でも、その感覚がすごく大切
中川 まさにそういう時代に入ってきている気がします。経営においては、トヨタの現場改善の時代、現場でより良くというのが上位としてあった時代から、サイエンスを中心に、統計的・数字的に全てを捉えて目標設定をして、ここまで改革していきましょうという時代がありました。で、いまはアートの時代だと言われていたりもして。
このアートというのは「美術的」ということではなくて、「うまく言葉にできないけど、なんかこっちの方がいいよね」っていう感覚的なことを「アート」という言い方をしています。で、日本の企業経営を見たときに、その「アート」だったり感覚的なことがわからないというか、わかっていても実行に移せないことが圧倒的に多いのではないかと思います。
それはなぜかというと、「株式会社」という仕組みの中で取締役会があって、そこで説明しないことにはなにも実行に移せない。でもさっきも言ったように、そもそも言葉にしにくいから説明ができないし、ましては「うまくいきますよ」「儲かりますよ」と言えるわけがないんです。だから日本ではそういうことが通らない。
でも、アップルのジョブズを代表するように、アメリカでは、それが「なんとなく感覚的にいいんだ」ということを彼がトップダウンで決めてしまえた。だから、iPhoneが生まれた。経営の面から見ても、いまは直感や感覚が大切だと言われています。それは「物」にも共通するような気がするんですね。だからこの「工芸と工業の次」というテーマにつながる話なんだなぁというように聞きました。
◆登壇者プロフィール

赤木 明登(あかぎ あきと) 塗師。1962年岡山県生まれ。中央大学文学部哲学科を卒業後、編集者を経て1988年に輪島へ。輪島塗の下地職人・岡本進さんのもとで修行後、1994年に独立。現代の暮らしに息づく生活漆器「ぬりもの」の世界を切り拓く。1997年にドイツ国立美術館「日本の現代塗り物十二人」展、2000年に東京国立近代美術館「うつわをみる 暮らしに息づく工芸」展、2010年に岡山県立美術館「岡山 美の回廊」展、2012年にオーストリア国立応用美術館『もの─質実と簡素』展に出品。著書に『二十一世紀民藝』(美術出版社)、『美しいもの』『美しいこと』『名前のない道』(ともに新潮社)、『漆 塗物物語』(文藝春秋)、共著に『毎日つかう漆のうつわ』、(新潮社)『形の素』(美術出版社)、『うつわを巡る旅』(講談社)など。
︎
中川政七(なかがわ まさしち) 株式会社 中川政七商店 代表取締役会長。1974年生まれ。京都大学法学部卒業後、2000年富士通株式会社入社。2002年に(株)中川政七商店に入社し、2008年に十三代社長に就任、2018年より会長を務める。日本初の工芸をベースにしたSPA業態を確立し、「日本の工芸を元気にする!」というビジョンのもと、業界特化型の経営コンサルティング事業を開始。初クライアントである長崎県波佐見町の陶磁器メーカー、有限会社マルヒロでは新ブランド「HASAMI」を立ち上げ空前の大ヒットとなる。2015年には、独自性のある戦略により高い収益性を維持している企業を表彰する「ポーター賞」を受賞。「カンブリア宮殿」「SWITCH」などテレビ出演のほか、経営者・デザイナー向けのセミナーや講演歴も多数。著書に『小さな会社の生きる道。』(CCCメディアハウス)、『経営とデザインの幸せな関係』(日経BP 社)、『日本の工芸を元気にする!』(東洋経済新報社)

鞍田 崇(くらた たかし) 哲学者。1970年兵庫県生まれ。京都大学文学部哲学科卒業、同大学院人間・環境学研究科修了。博士(人間・環境学)。専門は哲学・環境人文学。総合地球環境学研究所(地球研)を経て、2014年より、明治大学理工学部准教授。近年は、ローカルスタンダードとインティマシーという視点から、工芸・建築・デザイン・農業・民俗など様々なジャンルを手がかりとして、現代社会の思想状況を問う。著作に『BETWEEN THE LIGHT AND DARKNESS 光と闇のはざまに』(共著、Book B 2017)、『フードスケープ 私たちは食べものでできている』(共著、アノニマ・スタジオ 2016)、『知らない町の、家族に還る。』(共著、兵庫県丹波県民局 2016)『民藝のインティマシー 「いとおしさ」をデザインする』(明治大学出版会 2015)など。民藝「案内人」としてNHK-Eテレ「趣味どきっ!私の好きな民藝」に出演(2018年放送)。http://takashikurata.com/
→[パネルディスカッション① 「工芸と工業の次」ディスカッション 5/6 ] 近日、公開予定です。
パネルディスカッション① 「工芸と工業の次」哲学者・鞍田崇 1/6
パネルディスカッション ①「工芸と工業の次」 塗師・赤木明登 2/6
パネルディスカッション ①「工芸と工業の次」中川政七商店 代表取締役会長・中川政七 3/6
写真提供:さんち編集部
テキスト編集:中條 美咲
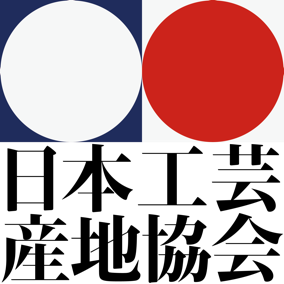
 メニュー
メニュー