-

【第2回レポート】パネルディスカッション① 「工芸と工業の次」ディスカッション 6/6
自分の手で「つくる」ということ 赤木 そう、一昨年くらいに『君の名は。』という映画が流行ったじゃないですか。あれって、飛騨高山あたりが舞台のモデルなんですよね。あの映画は、大きな隕石が落下してたくさん人が死ぬという厄災からの救済を描いた映画ですよね。 鞍田 うん。 赤木 で、そのストーリーに共感した人がたくさんいるのは、我々の背景に、そういう大きな厄災や大量死が起きる...記事を見る -

【第2回レポート】パネルディスカッション① 「工芸と工業の次」ディスカッション 5/6
土地とのつながりを求めて 赤木 先ほどの「土地とのつながり」の問題なんですけど、具体的に僕らは土地の中にもう一回戻って行くことはできないわけじゃないですか。柳宗悦*1さんが集めた収集物、要するに民藝館に展示されているような物というのは、人がまだ土地の中に埋め込まれていたように生きていた時代。*1)柳宗悦(やなぎ むねよし):日本を代表する思想家(1889年3月21日 – 19...記事を見る -

【第2回レポート】パネルディスカッション① 「工芸と工業の次」ディスカッション 4/6
なにに対する「共感」か 鞍田崇(以下、鞍田) ありがとうございます。中川さんのお話では、いまは憧れじゃなくて共感が求められているんじゃないかというご指摘がありました。赤木さんの実感はいかがでしょうか。 赤木明登(以下、赤木) まぁほんとに、中川さんとは25年くらいのお付き合いというか、最初は酒飲んで暴れているおっちゃんだったという話だったんですけど(笑)。チョット僕...記事を見る -

【第2回レポート】パネルディスカッション① 「工芸と工業の次」中川政七商店 代表取締役会長・中川政七 3/6
「売る」という感覚では生きていけないと思い、始めた店づくり 中川政七(以下、中川) 僕の場合、「中川政七商店」という会社が、家の商売としてもともとあって、16年前に家業に戻りました。当時、お茶道具が主流の商売をしていている一方で、社内で母親が生活雑貨的な商売を担当していて赤字だったので、まずはその部門を立て直すことから関わり始めていきました。 中川政七(...記事を見る -

【第2回レポート】パネルディスカッション① 「工芸と工業の次」塗師・赤木明登 2 /6
5年間の奉公時代に体得した「大きな糧」 赤木 明登(以下、赤木) 先ほどの飛騨職人学舎の若い人たちの挨拶がとっても素晴らしくて。 最初に僕も自己紹介をさせていただきますね。実は僕は、いまからちょうど30年前の1988年、東京でサラリーマンを4年間やっていたんですね。それから輪島で職人さんになろうと思い、一念発起しまして、いわゆる”脱サラ”をして、輪島に引っ越しました。 &n...記事を見る
工芸産地博&カンファレンス conference
入会案内
当協会に入会を希望される企業様は、下記ページをご閲覧いただき、「日本工芸産地協会入会申込書」のご提出をお願いいたします。
お問い合わせ
当協会へのお問い合わせは、下記フォームより受け付けております。
※平日(月~金)9:00~17:00の対応となります。
土日祝・お盆・年末年始のお問い合わせは順次対応させていただきます。
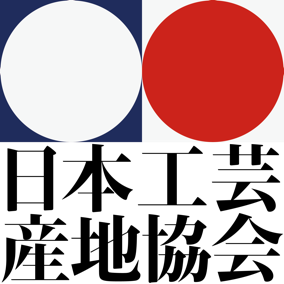
 メニュー
メニュー